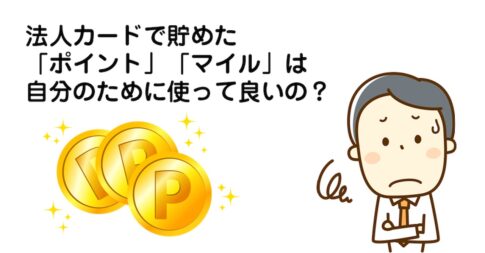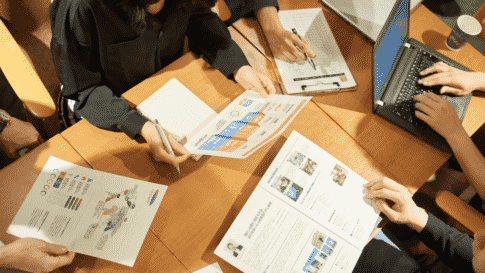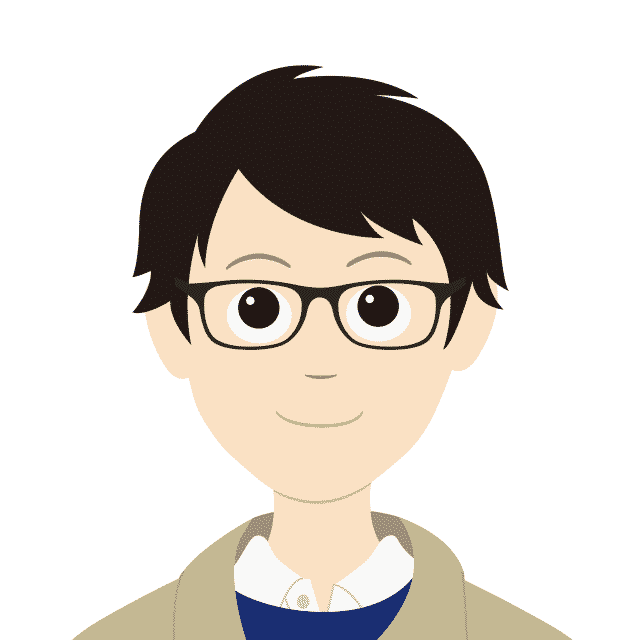法人カードの決済方式は2種類。法人決済型と個人決済型の違い
法人カードには「法人決済型」と「個人決済型」の2種類が存在し、利用者の立場や経理体制に応じて最適な方式を選ぶことが重要です。それぞれの特徴を理解することで、自社に合ったカード運用が可能になります。
法人決済型の特徴
法人決済型は、カード利用代金が会社の法人口座から一括で引き落とされる方式です。複数の社員が法人カードを利用しても、すべての利用額は法人名義で処理されます。
この方式は、経理担当がまとめて経費を管理できるため、経費処理の一元化や資金繰りの把握が容易になるのが特徴です。立替精算の手間が省け、経費処理が効率化される点もメリットといえます。
一方で、私的利用は禁止されるため、社員は業務目的にのみ利用することが前提となります。
個人決済型の特徴
個人決済型は、カード利用代金が利用者本人の個人口座から引き落とされる方式です。ビジネス利用に加えて、プライベート利用も可能であり、1枚のカードで用途を兼用できる点が魅力です。
経費として利用した分は、後から会社に精算を申請する流れとなります。そのため、社員は柔軟に利用できる一方で、経理側は申請の確認や精算対応が必要になり、業務負担が増えるケースもあります。
また、審査には個人の信用情報が反映されるため、申込者本人の信用状態によって発行可否が左右される点も特徴です。
選び方のポイント
- 経費精算を効率化したい企業や従業員数の多い法人は「法人決済型」が向いています
- 福利厚生や社員の利便性を重視する場合や、個人事業主が私用と兼用したい場合は「個人決済型」が適しています

法人カードの個人決済型が注目される背景
法人カードの個人決済型は、従来の「法人決済型」では対応しきれなかったニーズに応える仕組みとして広がりを見せています。その背景には、企業環境や働き方、金融市場の変化が密接に関係しています。
従業員の利便性と福利厚生ニーズの高まり
近年は出張やリモートワークの普及により、従業員一人ひとりが自ら支出を管理する場面が増えています。法人決済型ではすべての利用金額が法人口座で処理されるため、私的利用はできません。一方、個人決済型ならプライベートの支払いにも利用できるため、カード1枚で生活と仕事の双方を管理できます。これにより、従業員の利便性や福利厚生としての魅力が高まり、採用や定着にもプラスに作用しています。
クレジットカード市場の変化
個人向けクレジットカード市場はすでに飽和状態にあり、カード会社は新しい利用者層を求めています。法人カード市場は比較的成長余地が大きく、特に「個人決済型」はカード会社にとって利用額を増やす手段となっています。加えて、カード利用によるポイント還元やステータスサービスは個人ユーザーにとって魅力的であり、法人カードであっても「個人の満足度」を意識した設計が求められるようになっています。
企業の決済ニーズの多様化
従業員規模や業種によっては、必ずしも法人決済型が最適とは限りません。例えば、スタートアップや個人事業主では、経費と私用を1枚でまとめたいニーズが強く存在します。また、外部委託先や短期雇用スタッフにも柔軟にカードを提供できる仕組みとして個人決済型は適しています。経費精算システムの発展により、個人決済型でも効率的に経費処理ができる環境が整ったことも後押しとなっています。
税務・管理リスクへの対応
法人決済型では、私用利用が発生すると不正利用や税務上の問題に直結するリスクがありました。個人決済型であれば、支払いはあくまで従業員本人の口座から行われるため、会社資金を不正に流用されるリスクを抑えられます。この仕組みは内部統制の観点からも注目されており、コンプライアンス意識の高まりとともに導入が進んでいます。

法人カードの個人決済型を導入するメリット
法人カードの「個人決済型」は、法人決済型とは異なり、利用代金が個人の銀行口座から引き落とされる仕組みです。この方式を導入することで、法人経営者や個人事業主にとって多くの利点があります。ここでは主なメリットを整理して解説します。
ビジネスとプライベートを1枚で管理できる利便性
個人決済型の最大の魅力は、事業経費とプライベート利用の両方を1枚のカードで管理できる点です。法人決済型では私的利用が禁止されますが、個人決済型ならカードの利用代金は一度個人口座から引き落とされるため、日常の買い物や旅行などでも気軽に使えます。経費利用分は会社へ申請して清算する流れになるため、経費と私的支出の混同リスクを避けつつ、1枚で完結できる利便性が得られます。
ステータス性の高いカードを利用できる可能性
個人決済型の法人カードは、法人との契約をベースに個人の審査も行われるため、一般的な個人カードよりも高い利用限度額やグレードのカードを利用できるケースがあります。たとえばゴールドやプラチナクラスの法人カードに個人で申し込むのは難しくても、個人決済型を選ぶことでその恩恵を受けられる可能性があります。結果として、ステータス性の高いカードを保持しつつ、付帯サービスや特典を享受できる点は大きな魅力です。
充実した付帯サービスを個人でも活用できる
法人カードには、空港ラウンジ利用や海外旅行保険、ビジネスに役立つ優待サービスなど、通常の個人カードにはない特典が多く含まれています。個人決済型の場合、プライベート利用にもカードを使えるため、これらの付帯サービスを個人としてもフルに活用できます。
例えば、出張時には空港ラウンジを利用し、プライベートの旅行でも同じサービスを使えるため、福利厚生としての価値も非常に高まります。
社員への福利厚生強化
企業が従業員に個人決済型の法人カードを発行すると、年会費は法人経費として処理できるため、福利厚生の一環として提供できます。従業員はプライベートでもカードを利用でき、各種優待サービスやポイント還元を受けられるため、モチベーションや満足度の向上につながります。特に採用競争力を高めたい企業や、社員の待遇改善を図りたい企業にとっては効果的な施策となります。

法人カードの個人決済型を利用するデメリット
法人カードの個人決済型は、利便性や付帯サービスの面で魅力的ですが、導入にあたっては見逃せないデメリットも存在します。ここでは主な注意点を整理します。
経費精算の負担が増える
個人決済型は、カード利用額が一度個人口座から引き落とされます。そのため、業務で使用した経費は利用者が会社に申請し、後から精算を受ける必要があります。法人決済型であれば法人口座から直接引き落とされるため、経理処理はスムーズですが、個人決済型では利用者ごとに申請・承認・清算のプロセスが発生します。出張や接待が多い場合には、経理部門と利用者双方にとって事務負担が増加する可能性があります。
個人の信用情報に依存する
個人決済型カードの発行審査では、法人の信用力だけでなく、利用者本人の信用情報も重視されます。過去の延滞や多重債務などがある場合、カードの発行が見送られるケースがあります。法人決済型なら会社の業績や財務状況が基準となるため、個人の信用に左右されにくいですが、個人決済型では社員一人ひとりの信用情報が審査結果を左右します。
審査落ちが人事面に影響するリスク
個人決済型カードの審査に落ちた場合、その結果は会社に通知されます。理由は開示されませんが、信用情報に問題があると推測されれば、人事評価や配置転換に影響を及ぼす可能性があります。特に経理や営業など金銭管理に関わる部署では、信頼性を疑われる要因になり得ます。
福利厚生目的での扱いに注意が必要
個人決済型を福利厚生の一環として導入するケースもありますが、会社が年会費を負担する場合は課税対象となる可能性があります。税務上の処理を誤ると追加課税や指摘を受けるリスクがあるため、制度設計段階で顧問税理士や専門家に確認することが重要です。

法人カードの個人決済型が向いているケース
法人カードの個人決済型は、すべての企業や事業主にとって万能ではありません。特に以下のようなケースで導入を検討するとメリットを享受しやすくなります。
経費と私用を一枚で効率管理したい個人事業主
個人事業主にとって、経費と私用の支払いを複数のカードで分けるのは手間になりがちです。個人決済型であれば、1枚のカードで事業用・私用の両方を利用でき、事後に経費分を帳簿処理するだけで済みます。カード利用明細も一本化されるため、会計ソフトと連携すれば経費計上も効率化しやすくなります。
福利厚生を重視したい企業
従業員に法人カードを配布する際、個人決済型を選べば福利厚生の一環として魅力を高められます。例えば、空港ラウンジや海外旅行保険などの特典を社員がプライベートでも活用できるため、モチベーションアップや人材定着につながります。従業員にとっても「自分名義のカード」として利用できる安心感があります。
ステータス性の高いカードを利用したい場合
個人決済型の法人カードは、法人契約の枠組みを活用して一般的な個人カードよりも高いグレードのカードを保有できる可能性があります。結果として、ステータス性のあるカードを社員に付与でき、対外的な信頼性や顧客対応の印象を高める効果が期待できます。特に接待や海外出張が多い業種では有効です。
経理リソースが限られている小規模事業者
法人決済型は経費が自動的に法人引き落としとなり便利ですが、小規模事業者の場合、社員数や取引額が少ないため経理の複雑性はそれほど高くありません。このような規模では、個人決済型の柔軟性と特典の活用が経費管理の効率性を上回るケースもあります。

個人決済型を選べる代表的な法人カード
個人決済型の法人カードは、限られたカード会社が提供しています。それぞれ年会費や付帯サービス、決済方式に違いがあるため、利用目的に応じた選択が重要です。ここでは代表的な3種類を紹介します。
三井住友コーポレートカード
三井住友コーポレートカードは、コストを抑えて導入できる点が強みです。個人決済型と法人決済型の両方に対応しており、必要に応じて選択できます。
一般カードとゴールドカードの2種類があり、一般カードは初年度1,375円(税込)、2年目以降も1会員につき440円(税込)と比較的安価です。追加カードの年会費には上限があるため、多数の社員に配布してもコストが膨らみにくい仕組みになっています。
ただし、アスクルやレンタカーサービスなど一部の法人向け優待は個人決済型では利用できない点に注意が必要です。
American Express(アメリカン・エキスプレス)Corporate Card
アメリカン・エキスプレスのコーポレートカードは、ステータス性が高く、国際ブランドとしての信頼感が強いカードです。
最大の特徴は「個別請求・一括支払方式」が選べることです。これは社員ごとの利用明細をもとに経費分だけを会社がまとめて支払う仕組みで、通常の個人決済型に比べて経費精算の手間を大幅に軽減できます。
空港ラウンジや旅行傷害保険、充実したコンシェルジュサービスなど、法人カードの中でもワンランク上の付帯サービスを利用したい企業や個人事業主に適しています。
UCコーポレートカード
UCコーポレートカードも、個人決済型と法人決済型の両方を選択できます。年会費は発行条件によって異なりますが、福利厚生サービスやJALオンラインサービス、タクシーチケットなどビジネスシーンに直結する付帯サービスが充実しています。
一般カードには旅行保険などが付帯されていないため、保障を重視する場合はゴールドカードを選ぶと良いでしょう。さらに、ETCカードを複数無料で発行できるため、社用車を多く使う企業にも向いています。

法人カードの個人決済型を利用する際の注意点
法人カードの個人決済型は便利な一方で、導入後にトラブルが起きやすい仕組みでもあります。利用にあたっては事前にルールや運用方法を明確にしておくことが欠かせません。以下のポイントを押さえておくと安心です。
経費精算ルールの徹底
個人決済型では、社員が立て替えた経費を会社が清算する仕組みになります。経理部門が混乱しないように、精算フローを事前に定義しておくことが重要です。
例えば以下のような点を明確化しておくとトラブルを防げます。
- 経費として認められる範囲(交通費、宿泊費、接待費など)
- 領収書や利用明細の提出期限
- 清算申請のフォーマットや承認フロー
これを徹底しないと「経費に含められるかどうかの判断があいまい」「清算が遅れて資金繰りに影響する」といった問題が起こりやすくなります。
清算期限と利用範囲の管理
個人の口座から引き落とされるため、社員の負担を軽減するには清算のタイミングを明確にすることが大切です。
例えば「翌月末までに清算完了」「出張終了から7日以内に申請」といった期限を設けると、社員側のキャッシュフロー悪化を防げます。
また、プライベート利用も可能である点は魅力ですが、あくまで限度額の範囲内で利用する必要があります。業務に関係ない支出が多くなると、限度額不足で業務に支障をきたす恐れがあるため注意が必要です。
税務上の取り扱い
法人が個人決済型を福利厚生目的で導入する場合、税務上の扱いにも注意が必要です。
例えば、社員のプライベート利用分を会社が補填してしまうと「給与」とみなされ課税対象になる可能性があります。福利厚生として認められるかどうかは経費の性質や利用状況によって異なるため、税理士や顧問会計士に確認しておくのが望ましいです。
信用情報への影響
個人決済型は社員本人の信用情報に基づいて審査が行われるため、カード利用や返済状況が個人の信用履歴に反映されます。万が一支払い遅延が発生すると、社員個人の信用スコアに悪影響を与えるだけでなく、企業イメージにもつながる可能性があるため、利用者への説明も欠かせません。

法人カード導入時の比較検討ポイント
法人カードを導入する際には、経営者や個人事業主にとって重要となる判断材料が多く存在します。単に「年会費の安さ」や「知名度」で選んでしまうと、後々の運用で不便さやコスト増につながることがあります。ここでは導入前に必ず確認すべき比較検討ポイントを整理します。
年会費・追加カード費用
法人カードは本会員だけでなく追加カードを発行するケースが多いため、発行枚数によるコスト増を見落とさないことが大切です。カードによっては追加会員の年会費が低額に設定されているものや、一定枚数までは無料のものもあります。従業員数や利用予定枚数を前提に、長期的にかかる維持コストを試算しておくことが必要です。
ポイント還元・マイル付与の仕組み
法人カードでも個人向けと同様にポイントやマイルが付与される場合があります。ただし「法人決済型」ではポイントが会社に集約される一方、「個人決済型」では社員個人に還元されるケースが多いです。福利厚生として従業員にメリットを持たせたいのか、経費効率を重視して会社に集約したいのかによって最適なカードが変わります。
付帯サービス・保険内容
出張や接待が多い企業では、空港ラウンジや海外旅行保険、ショッピング保険の有無は大きな比較材料です。特に海外出張がある場合には、傷害保険の補償額や緊急時のサポート体制を必ず確認しておくべきです。ETCカードや福利厚生サービスが付帯しているかも実用面では重要です。
利用限度額と審査基準
法人カードはカード会社によって限度額の設定や審査の重視ポイントが異なります。法人決済型は会社の信用力が主に問われるのに対し、個人決済型は利用者本人の信用情報も影響します。事業規模や従業員の信用情報の状況に応じて、どちらが導入しやすいかを検討する必要があります。
法人決済型と個人決済型の選択
最大の分岐点は「会社が一括管理するか」「個人が一度立て替えるか」です。法人決済型は経費管理が効率的で不正利用のリスクも低いですが、私用利用はできません。個人決済型は私用と併用でき、福利厚生面では魅力がありますが、経費精算の手間や審査リスクを伴います。導入目的と運用ルールに合わせて選択することが重要です。